中学受験は、子どもにとっても保護者にとっても、大きな決断のひとつです。

「中学受験に向いている子とは?」「うちの子でも挑戦できる?」
と不安に感じる方も多いですよね。
わが家は、1番目と2番目の子が中学受験をしました。
2人は珠算や公文に通っていて、ある程度の学力がありました。
また、夢の近道のために「中学受験をしたい」という気持ちがあり、性格的にも挑戦できると感じたので挑戦しました。
でも3番目の子に関しては、今のところ受験の予定はありません。
今後の成長過程で変化はあると思いますが、3番目は忍耐力や性格から向いていないと感じているからです。
中学受験に向いているいるのか、どんな子が向いているのかを理解して受験するかを判断していきましょう。
また、合格するための親のサポートがとても重要になってきます。
子どもの性格や現状をしっかり向きあって、子どもと相談して決めていきましょう。
中学受験をすることが決まったら、最初のステップは塾選びです。
子どもに合った塾を見つけないと、勉強を始めても成績が上がらない可能性があるんです。
そのためにも、「塾選」のリアルな口コミや体験談を参考にすることをおすすめします↓
わが子2人の中学受験の体験談はこちら⬇️
沖縄で2人の子どもが中学受験した体験談と知っておきたい中学受験情報
記事の信頼性
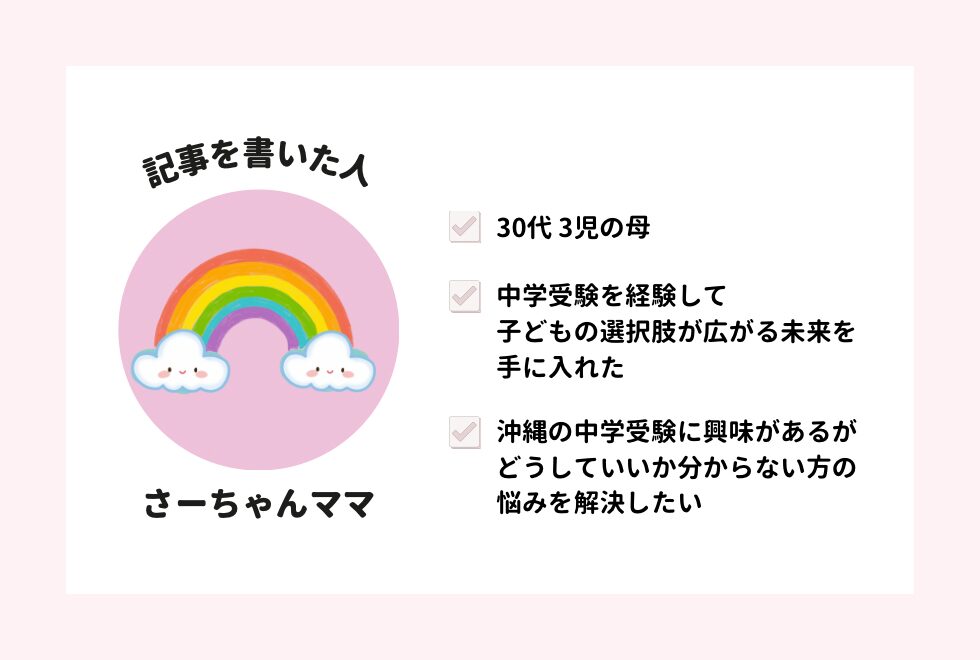
中学受験が向いている子の特徴
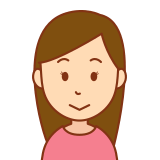
うちの子、中学受験に挑戦したいそうです。
受験に向いているのかな…?
中学受験はが向いているかの判断は、次の3つに当てはまるかチェックしてみましょう。
でも、当てはまらないからといって受験に向いていないのではありません。
子どもの努力や環境によって変えることは可能なんです。
それぞれ詳しく確認していきましょう。
学ぶことが好き

全ての教科だけではなく、1つでも好きな教科がある子はおすすめ!
好きな教科がある子は、学習の楽しさを知っています。
学習の楽しさを知っている子は、この経験があることで、他の教科にも前向きに取り組む可能性が高いです。
うちの子は算数が大好きで、問題を解くことに楽しさを感じていました。
そのため、苦手な教科でも「やってみよう!」と挑戦する気持ちを持つことができたんです。
また、成績が上がると勉強が楽しくなるので、さらに意欲的に取り組むようになります。
だから、学ぶことが好きな子は、中学受験に向いています。
自律している
自分で計画的に学習に取り組めるかも大事!
勉強する時間を計画的にできる子は、成績アップにつながりやすいです。

そのためには、親が時間の管理をしてあげることも必要になってきます。
こどもの自律のためには、はじめは親の手助けも必要になってきます。
わが家は、タイマーを使って勉強やゲームのなどの時間を管理していました。
その結果、勉強とのメリハリを意識するようになり、計画的に学習できるようになったんです!
自分で学習の計画を立て、実行できる習慣が身についていることも大切になってきます。
目的がある
志望校が明確にしていないと、目標を見失しないやすくなってしまいます。
「なぜ勉強をするのか」を明確にしておくことが大切です。

学校の見学をしたり、オープンキャンパスに参加するのもおすすめ。
学校の雰囲気や実際に授業を体験することで、「この学校にいきたい!」という気持ちが強くなります。
目標を持ち続けるためにも、親子でしっかり確認しながら、受験へのモチベーションを高めていきましょう。
これらのポイントを確認しながら、お子さんの気持ちを大切にサポートしていきましょう!
中学受験が向いていない子の特徴

中学受験は誰にでも向いているわけではなく、子どもの性格や学習スタイルによっては負担が大きくなってしまうこともあるんです。
特に、以下のような特徴がある場合は、受験を乗り越えるために親のサポートがより必要になってきます。
- 自己管理が苦手 … 計画的に勉強するのが難しい
- 目的意識がない … 受験の意味や将来の目標を持っていない
しかし、1番大切なのは子どもの気持ちと意欲です。
私が1番目の子に中学受験を考えたのは、将来の選択しがたくさん増えるようにという願いからです。
でも、親の思いだけでは中学受験をすることはできません。

子どもを「中学受験に向いている子」に変える方法は2つ!
中学受験に合格するためには、子どもの意欲を引き出すことが大切です。
親が適切なサポートをしながら、子どもがしっかり取り組める環境を整えていきましょう。
そのためにも、子どもにあった塾選びは大切になってきます。
塾の情報か一目で分かる「塾選」を使って、無料体験から始めることをおすすめします。
知っておきたい!中学受験するメリットやデメリット
中学受験には、たくさんのメリットとデメリットがあります。
子どもの性格や状況、親の協力体制によって向き不向きが変わってきます。
メリット・デメリットをしっかり理解して、中学受験は決めていきましょう。
わが子は、珠算や公文教室に通っていたため、ある程度の学力がありました。
また、将来の夢があり意思もあったため、少し遅かったですが、小学5年生の夏から受験勉強をスタート!

「やりたい!」と本人の意思があったものの、学力の差に戸惑いもあり、目標を見失うことも…。
一緒に問題を解いたり、プラスになる声かけしたりしてモチベーションupにつなげました。
中学受験は、親のサポートがとても必要になってきます、
子どもとしっかり話し合ったうえで、慎重に決めていきましょう。
向いていない子は中学受験しないほうがいいの?中学受験をする意味は?
中学受験は子どもにとって大きなチャレンジになります。
子どもだけではなく、親もかなりの精神的なサポートが必要になってきます。
長期間の勉強と向き合う必要もあり、子どもの性格や成長段階によっては、向き・不向きの場合があります。
向いていない可能性があるケース
- 長時間の勉強に集中できない
- プレッシャーに弱く、過度にストレスを感じやすい
- 親が希望していて、本人にやる気がない
- 自己肯定感が低く、失敗への耐性が弱い

無理に受験をさせることで、勉強嫌いになったり、自信をなくしたりする可能性があるんです。
わが子も、合格を胸に学習を始めましたが、塾生との学力の差に、なかなか勉強に前向きになりませんでした。
でも、「志望校に合格したい」という気持ちはしっかり持っていました。
勉強が分かるようになってくると、楽しくなりモチベーションも上がり、自ら勉強するようになりました。
だから、その時は向いていないように見えても、本人のやる気や環境次第で変わることもあります。
無理に進めるのではなく、その都度子どもとよく話し合って、判断することが大切です。
中学受験の向いている子・向いていない子のよくある質問
もし中学受験にチャレンジしてみようとなった時、大切なことは何ですか?
子どもの「受験したいという気持ち」と「学習に対する意欲」が、挑戦するときに大切になってきます。
親が中学受験をさせたいと思っても、実際やるのは子ども。
中学受験のメリット・デメリットや、勉強量など、子どもに求めることが多いので、子どものやる気や意欲がないと合格することは難しいです。
なぜ、中学受験をするのかを明確にしていきましょう。

親のサポートがとても大切!
大好きな親が、「応援してくれる」「サポートしてくれる」ことは、子どもの励みになり心の支えになります。
わが家は、明確な夢が決まっていました。
そのため、夢を叶えるためには中学受験をした方が近道だと話をしたことがきっかけでした。
子どもが挑戦のしたいという気持ちを実現させるために、塾選びからスタート。
塾に通い始めて、実力の差につまずくこともありましたが、毎日コツコツと勉強を続けることで、成績は目に見えて上がってきました。
塾は、子どもとの相性が重要!
そのためにも、「塾選」で無料体験をして、子どもに合った塾を見つけることからおすすめします。
沖縄で塾を探すならこちら⬇️
中学受験の経験者の親でも、自分の子には中学受験をさせたくないと思うこともありますか?
中学受験の大変さを知っているからこそ、「させたい・させたくない」ではなく、「したい・したくない」の子どもの気持ちを重視します。
「努力すること」と「経験させること」は経験させたい、1度きりしかない中学受験をチャレンジして欲しいと考える親が多いように感じます。

私は中学受験は経験していません。
存在すら知りませんでした。
でも、子どもにたくさん学んで、未来の選択しを増やしてじぶんに合った道を見つけて欲しいと想い中学受験の進めました。
中学受験は、志望校に合格することが目標ではありますが、合格するまでの道のりが奥深いものです。
大変だからこそ、親の思いではなく、子どもの思いを明確のして決めていきましょう。
まとめ
中学受験は「子どもの意欲」と「親のサポート」が大切になってきます。
学ぶことが好き・自律している・明確な目的があることが中学受験に必要になってきますが、サポートや環境次第で成長することはあるんです。
しかし、自己管理が苦手だったり、目的意識が持てなかったりする子にとっては、受験が大きな負担となることも考えられます。
無理に受験を進めるのではなく、子どもの気持ちを大切にし、話し合いながら進めていくことが大切です。
中学受験には、「将来の選択肢が広がる・目標達成の達成感を得られる」などメリットがありますが、長時間の勉強や精神的な負担いうデメリットも…。
だからこそ、子どもの「やりたい」という気持ちと、親の適切なサポートが成功のカギとなります。
子どもに合った塾選びや学習環境を整えることも大切です。
受験を通して「頑張る力」「あきらめない心」を育てられるよう、親子で一緒に進んでいきましょう。
そのためにも、子どもに合った塾選びから始めることをおすすめします。


